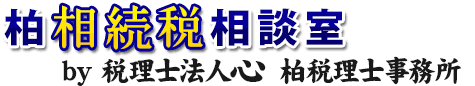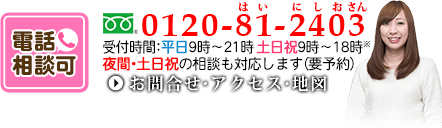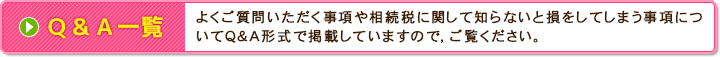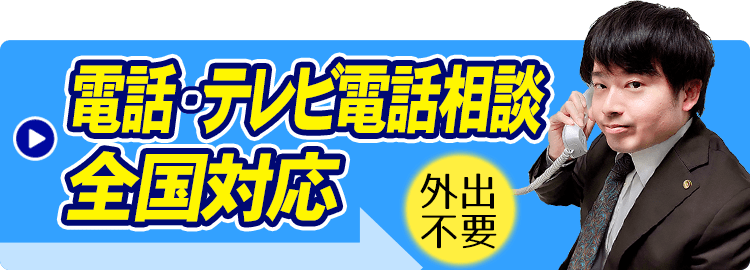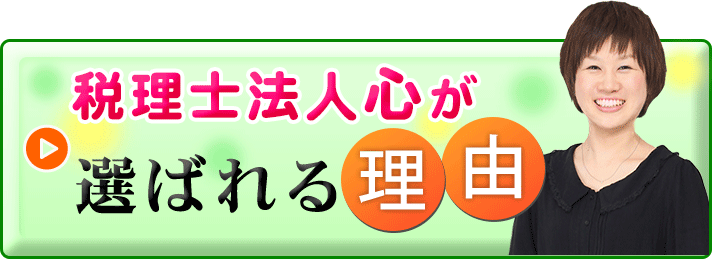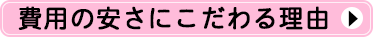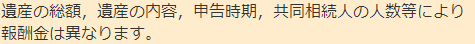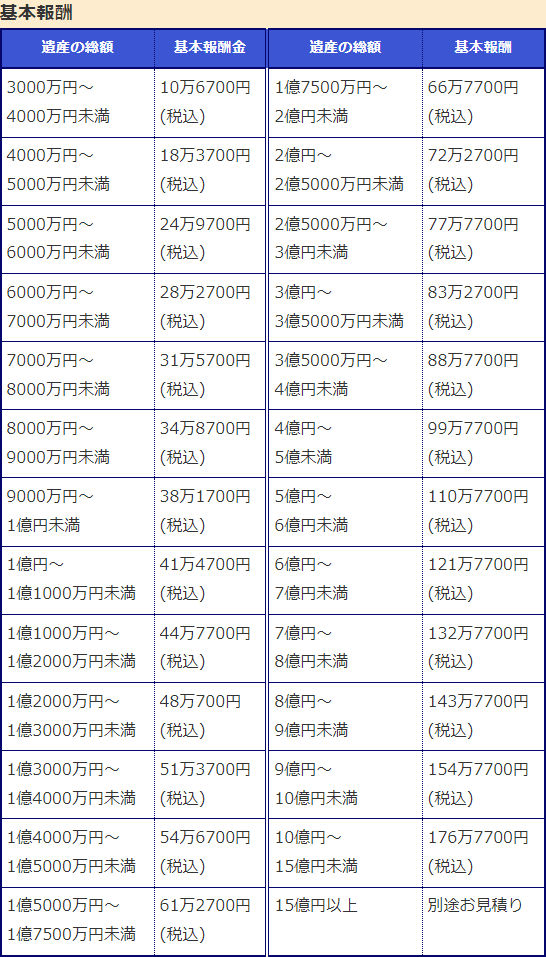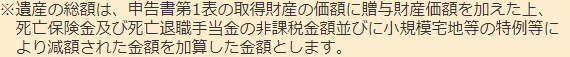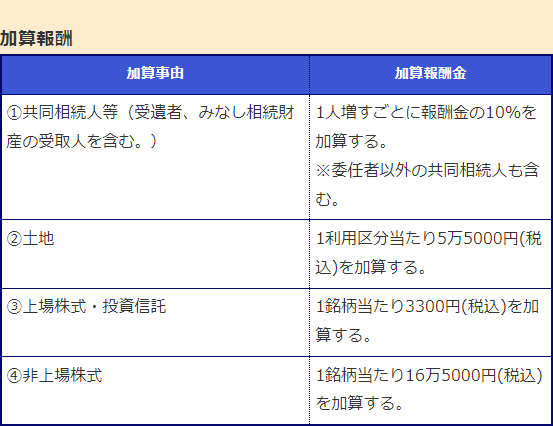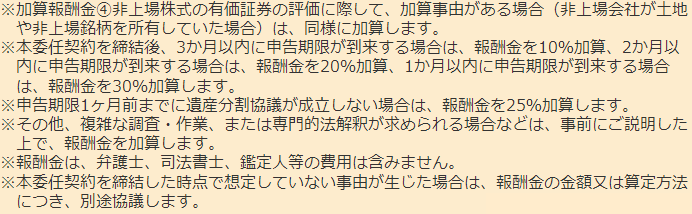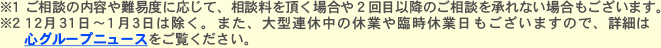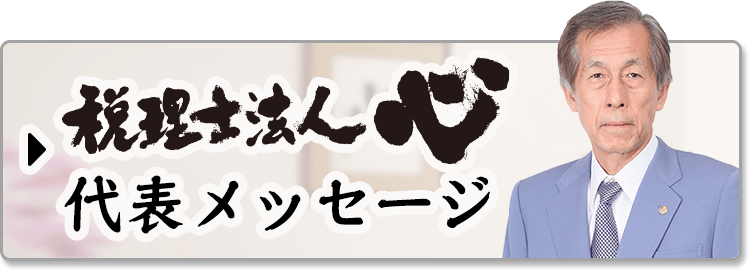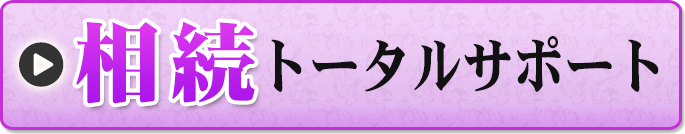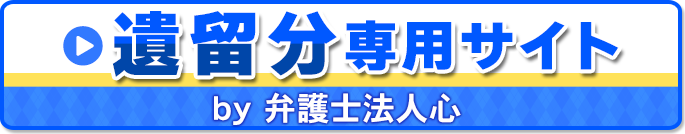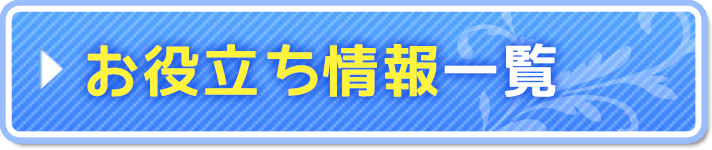「相続税の計算」に関するお役立ち情報
相続税の基礎控除はどのように計算するのか
1 基礎控除額
相続税は、基礎控除額を超えた場合に、初めて発生します。
この基礎控除額の計算方法は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
具体例を挙げて、説明します。
夫が亡くなり、法定相続人が妻と子1人の場合、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人(妻と子)=4200万円となります。
次に、夫が亡くなり、法定相続人は妻と子3人の場合、基礎控除額は、3000万円+600万円×4人(妻と子3人)=5400万円となります。
2 法定相続人とは
上記各ケースで見たように、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。
そのため、相続税の基礎控除額を計算する際、法定相続人が誰であるかを把握することが重要となります。
法定相続人とは、民法によって定められた相続人となる人のことを指します。
被相続人に配偶者がいた場合は、配偶者は必ず相続人となります(民法890条)。
配偶者以下の相続人については、順位が決められており、第一順位は子(亡くなっている場合は孫)となります(民法887条)。
第二順位は、第一順位の相続人がいない場合、父母(亡くなっている場合は祖父母)となります(民法889条1項1号)。
第三順位は、第一順位も第二順位も相続人がいない場合、兄弟姉妹となります(民法889条2項1項2号、同条2項)。
兄弟姉妹も亡くなっている場合はその子(被相続人との関係では甥姪)が相続人となりますが、甥姪の子が再代襲して相続人になることはありません。
3 代襲相続が発生した場合
相続税の基礎控除額を計算するにあたり、代襲相続が発生していた場合は十分注意が必要です。
代襲相続が発生しており、法定相続人の数が増えた場合は、それに応じて基礎控除額も増えることになります。
例えば、夫A、妻B、子C、子Cの子である孫Dと孫Eがいたとします。
夫Aが令和7年7月15日に亡くなり、相続が発生した場合、妻Bと子Cが健在であれば、法定相続人は妻Bと子Cになります。
そのため、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×2人となり、4200万円になります。
ここで、子Cが令和元年に、既に亡くなっていた場合はどうなるでしょうか。
この場合、子Cが既に亡くなっているので、孫Dと孫Eが代襲相続人となり、相続人は、妻B、孫D及び孫Eとなります。
そのため、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人となり、4800万円になります。
このように、代襲相続が発生した場合などは、法定相続人の数が変わり、相続税の基礎控除額も増えることがありますので、十分注意することが必要です。
4 相続放棄をしている人がいた場合や養子がいた場合
相続放棄をしている人がいた場合であっても、相続税の基礎控除額を計算するにあたっては、法定相続人の数に含めることができます。
また、被相続人に養子がいた場合は、実子の数によって、法定相続人に含めることができる人数が変わってきます。
被相続人に実子がいる場合は、法定相続人としてカウントできる養子の数は、1人となります。
被相続人に実子がいない場合は、法定相続人としてカウントできる養子の数は、2人となります。
なお、被相続人との間で、特別養子縁組(民法817条の2参照)が成立している場合の養子は、実子としてみなされますので、法定相続人の数に含めることができます。
相続税の課税の対象とならない財産 配偶者に対する相続税額の軽減