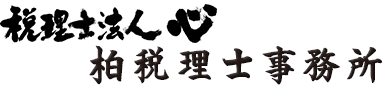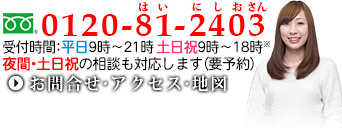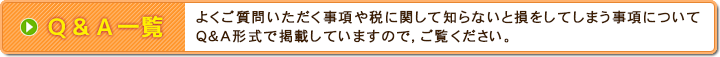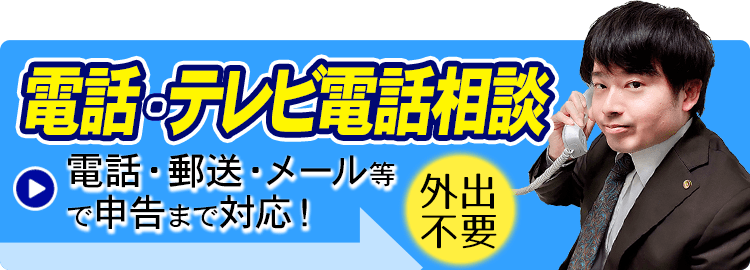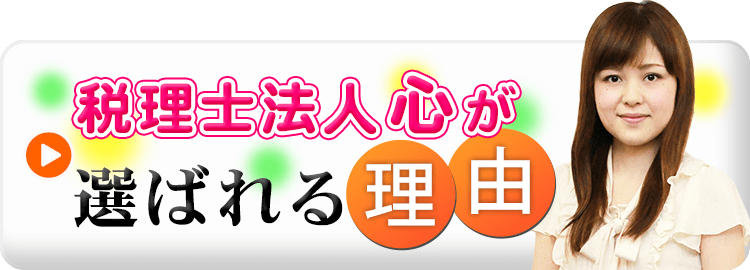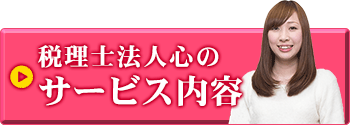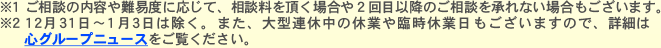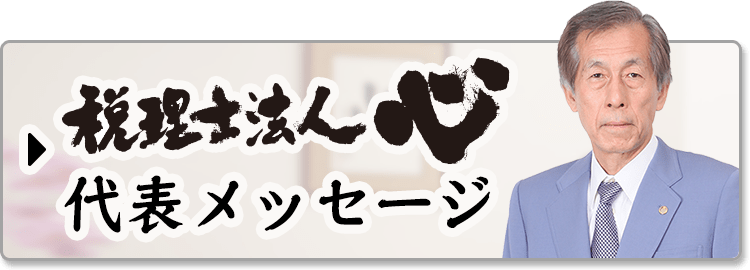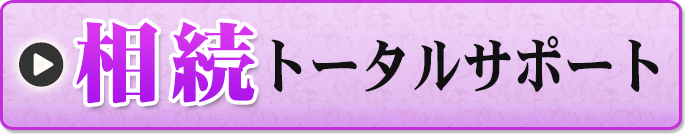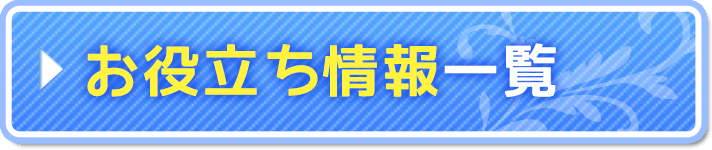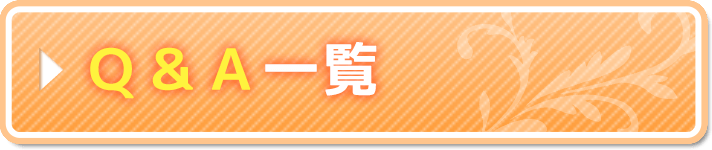贈与が名義預金とみなされないために注意すること
1 贈与と名義預金
贈与とは、一方の当事者が自己の財産を無償で他方に与える意思を持ち、相手方がそれを受け取ることで成立する契約です。
他方、実務上、特に相続税の申告において問題となるのが名義預金です。
これは、例えば子や配偶者などの名義の口座に預金されていても、実質的に贈与が成立していなければ、その預金は贈与と認められず、贈与者(多くは親や祖父母)の財産とされる可能性があります。
こうした名義預金と判定されないためには、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
2 贈与契約の成立要件を満たすことの重要性
贈与は契約行為ですので、考えると当たり前のことなのですが、贈与される側と贈与を受ける側の意思の合致が必要で、片方だけの一方的な意思によって贈与はできません。
つまり、受贈者が贈与を受けたことを知っており、受け取る意思を持っていたことが重要です。
これを証明するためには、贈与契約書を作成することが望ましいです。
贈与の事実を明確に示すために、「誰が」「誰に」「いくら」「いつ」「どのような財産を」贈与したのかを記載した契約書を作成します。
契約書は可能であれば公正証書として残すとより信頼性が高まりますが、もちろん自筆でも構いません。
その際には、署名と押印を、贈与者および受贈者の両者で行うことが重要です。
印鑑は認印でも問題ないのですが、贈与者・受贈者の実印の押印があると、贈与の合意があったことをより強く証明できます。
なお、贈与契約書を作成するだけでなく、実際にお金が移動している証拠を残すことも重要です。
現金で贈与すると、本当にお金が移動しているのか、わかりにくい場合があります。
例えば、家に金庫が一つしかなく、親のお金と子どもお金が一緒の金庫で保管されている場合に、現金で贈与してしまうと本当に贈与があったのか、証明することが難しくなります。
そのため、銀行口座を通してお金を振り込み、お金の移動の事実を対外的にはっきりできるようにしましょう。
3 名義預金と預金口座の実質的管理
名義だけでなく、実質的な預金管理の実態も名義預金かどうかを判断する重要な要素となります。
具体的には、受贈者自身が通帳・口座の届出印・キャッシュカード・暗証番号を保管・管理しているかどうか、という点です。
名義人である受贈者が、実際に預金を管理していることが必要です。例えば、親が子どもに金銭を贈与したと言っていたとしても、通帳や
届出印を親が保管していた場合、子どもが暗証番号を知らない場合は、実質的に贈与が成立していないと判断される可能性があります。
また、預金の出し入れを受贈者が行っていることも重要な要素です。
受贈者が日常的に預金口座を利用していれば、名義預金とは指摘されにくくなります。
逆に、贈与者が自由に入出金を行っていると、口座の名義は、形式的な名義にすぎず、実質的には贈与が成立していないとみなされてしまいます。
4 定期的な贈与の分割ではなく、都度契約を交わす
また、贈与で気をつけるのは名義預金だけではありません。
年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない基礎控除がありますが、これを利用して毎年同額を繰り返し贈与していると、連年贈与とみなされ、合計額が1年で贈与されたとみなされることがあります。
そのため、毎年贈与契約書を作成することが重要です。
なお、贈与する意思の確認(口頭でも可)を行うことが重要で、契約書に限らず、贈与の意思確認の記録(メールや手紙など)を残しておくと、税務調査の際の税務署への説明する資料として有効です。
5 名義預金と贈与税申告
110万円を超える贈与については必ず申告をするようにしましょう。
贈与税申告を怠ると、そもそも贈与ではなかったと考えていたのではないかということになり、税務署に贈与の事実を認めてもらえず、相続時に名義預金として相続財産に組み込まれる可能性があります。
そのようなことにならないように、申告義務がある場合には必ず申告し、申告書の控えと納税を証明する振込用紙等の保管をしておくことが大切です。
贈与税の基礎控除内(年間110万円以下)であれば申告不要ですが、あえて贈与税の申告をすることで、贈与の事実を明確に残すという人もいますが、それだけで贈与の事実を証明できるわけではなく、これまで述べたような要素を多角的に検討して判断されるということを意識しておく必要があります。
6 名義預金と受贈者が未成年の場合の注意点
受贈者が未成年の場合、贈与契約の成立には法定代理人(通常は親)が関与します。
未成年者の名義で預金口座を作っても、実際には親が管理しているケースが多いのが実情です。
未成年者自身が使う目的があるかどうかという観点から、たとえば学費や習い事の費用など、明確な使用目的があり、親が代理で支出している場合は受贈者の未成年者の預金と認められやすくなります。
親が未成年者自身のために使わないお金を自由に動かしていると、例えば、生活費が足りなくなったから一時的に借りる等、名義預金と判断されやすくなります。
また、成年に達した後は、子どもといえども、本人に管理させるようにしましょう。
18歳となり、成人した後に、その預金を本人が自由に使っている実態があると、贈与の有効性が高まります。
成人になると、基本的に、親が子どもの財産を管理する法的な根拠がなくなることに注意が必要です。
7 贈与と名義預金の注意点
名義預金とされないためには、形式ではなく実質が問われます。
つまり、贈与があったことを書面で証明できるようにしつつ、実質的にも受贈者が財産を自由に管理・使用できているかどうかが重要なのです。
特に、相続税の調査では過去の預金移動が厳しくチェックされ、名義預金と判断されると、多額の追徴課税が発生することがあります。
そのため、贈与契約書の作成、贈与税の申告、預金管理の実態、通帳や届出印の保管状況など、日頃から適切に対策を講じることが重要です。
不安がある場合は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。